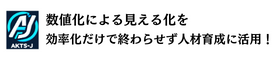仕事の規則やルールを守らせるには?(改訂版)


会社では、
規則やルールを守らせる為に定期的にミーティングを行い、
さまざまな掲示物を貼っています。
それでも、守られていないのが現状です。
規則やルールが守られない事で、
大きなミスや重大な事故・事業の停止に発展することが多々あります。
そのことを怖れているからこそ、
会社では、規則やルールを守らせる為に様々な施策を行なっています。
それでも、守れない場合が多々あります。
守れないことで
大きなミスや重大な事故に発展する
可能性があるにも関わらず、なぜ守られないのでしょうか?
あなたは、なぜだと思いますか?
必要性を感じないから?
これぐらいなら、大丈夫だと思い込んでいるから?
守られない大きな原因は、
規則やルールを守りながら、
仕事の生産性アップや効率化を求められるからではないでしょうか?
ルールや規則を守ると多くの場合、
確認事項や仕事の手順が増え、
生産性や効率に影響を与えることが多々あります。
だからみんな、
慣れからくるこれぐらいはいいだろうと言う自己判断で、
ルールや規則を守らなかったり、軽視をしてしまいます。

そして重大なミスや事故が起こると、
職場のリーダーや管理職は、
なぜルールや規則を守らなかったのかと、
問いただしてきます。
毎日の仕事において生産性・効率のアップを
促す課題や指示をしています。
勤続年数が長いと、
仕事のコツや妥協点がだんだん分かってくると、
ルールや規則でも、守るべき重要なポイントが分かってきます。
なので、そのポイントを外さないように仕事の生産性・効率アップを行います。
問題なのは、勤続年数が短い1年目や2年目の人です。
新卒の人であれば、仕事が遅くても、普通であれば注意されません。
ただし、同業からの転職者やある程度
経験を持っている派遣社員の場合は違います。
転職者や派遣社員は、
どんな仕事であれ、それなりの経験があり、
基本的な事は出来るという先入観念願を持たれています。
なので、
ルールや規則の厳守と同時に、生産性や効率を求められます。
この場合の問題は、どんなにその仕事に慣れていなくても、
規則やルールの厳守と生産性・効率アップが求められる事です。
そしてミスなどをすると、「なぜ、ミスをしたのか」、
「なぜ、ルールや規則を守らなかったのか」と問いただしてきます。
仕事を教えている人は、仕事に慣れていない相手に対して、
無意識に減点方式の仕事の評価で、
規則・ルールと生産性・効率アップの板挟みに追い込んでいます。
規則・ルールの厳守と仕事の生産性アップ・効率化。
もちろん、両方とも大切です。
大切ですが、
残念ながら日頃の忙しさの為に目の前の仕事を失敗なく、
早く行わさせる事に焦点を当ています。
本来、入社して1〜2年間は、
仕事を覚えさせ、慣れさせる事が最優先です。
その期間に生産性・効率アップを求めてしまうと、
規則やルールまで意識が回らなくなってしまう可能性があります。
役職が上がると、自然と現場と距離が離れ、
規則・ルールと生産性・効率アップの両立する為の理想論を提案します。
その為の目的と目標を作るきっかけを与える必要があります。
ただし、現場の本音は「そんなのは無理です」と思っているのが現実です。
慣れ親しんだ仕事の状況や流れ・段取りを変えたくないという
気持ちが大きく関係しています。
無意識に拒否反応を起こしてしまいます。
どんなに素晴らしいアイディアや行動力があろうとも、
1人で出来る事は限られています。
アイディアを実現出来るだけのスキル・知識を持っている人を雇わなくて、
望む結果は得られません。
家具などを6畳の部屋に置く事は、物理的に無理です。
アイディアを考えるのが無理と初めから諦めてしまっている場合です。
何故、考える事を放棄してしまっているのか、その原因を知る事が大切です。
会社で決められた規則やルールを守るのが嫌だという人は普通はいません。
どのような結果を生み出すかという情報を共有します。
仕事に慣れていない人に対して、
規則やルールを守りながら、
同時に生産性アップ・効率アップを求めるというのは、
「二兎を追う者は一兎をも得ず」という事になり、
余計なプレッシャーを与えてしまいます。
「二兎を追う者は一兎をも得ず
【意味】
二兎を追う者は一兎をも得ずとは、
欲を出して同時に二つのことをうまくやろうとすると、
結局はどちらも失敗することのたとえ。」
少なくとも、
勤続年数が2年未満の人に対しては、
規則・ルールの厳守を最優先にさせる事が必要です。
そして、3年以上5年未満の人に対しては、
規則・ルールを厳守させながら、
少しづつ仕事の生産性・効率アップをさせるように
指導していく必要があります。
勤続年数が5年以上にもなれば、
規則・ルールの厳守は当然として、
仕事の生産性・効率アップが出来るように
仕事の指導をしていく必要があります。
その際、先ほどお伝えした
3つの無理を言わせない・感じさせない環境作りを
行っておく必要があります。
ただ、
「今の時代、そんなにのんびり仕事を教える時間が無い!」
と言われるか方が多いと思います。
だからと言って、時間を惜しんでは人財を育成する事は出来ません。
時間をかけてでも、人財を育てるか。
時間を惜しんで、人罪を育てるか。
規則やルールを守るのは、
人財と人罪、どちらかの人なのか考え、
長期的視野で限りある時間を活用する必要があります。
規則やルールを守らせるとは、人財を育てる事なのです。
山本五十六氏の
「やってみせ、言って聞かせて、
させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。
話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」
という言葉にあるように、
人を育て、成長させるには時間が必要なのです。
仕事を教える人にこそ、
教えている相手が成長する時間を楽しみ、
待てる心の余裕が必要なのです。




初めての方へ

現場力メソッド

経験知