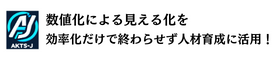仕事はアートであり、デザインすること
藤澤氏は、「経営は、アートである」と持論を持っている。
これを
「美しい企業とは、楽しさ、おもしろさ、
ゆとりを配慮するだけでなく、社員の働く意欲に正面から答える、
さまざまなシステムを用意している企業である。」
(「ホンダを作ったもう一人の創業者」より。)
と藤澤氏は表現している。
そして、本田宗一郎氏の言葉で、
「人には誰しも、得意なものと不得意なものがある。
そこでこそ、個性が生まれ、得意分野で活躍し、
不得意分野を補い合って生きていくという
世の中の仕組みが成り立つ。
職場においてもこの仕組みを十分活用すべきである。」
(「ホンダ神話 1」より。)
と言うのがある。
この事を判っているからこそ、
藤澤氏は、それぞれの個性を生かす為に、
思考錯誤しながら組織作りをしたのではないかと思う。
藤澤氏は、芸術・美術に造詣が深く、
常盤津を唸らせれば玄人はだし。
そして、ワーグナーのオペラは、
和服姿でドイツまで聴きに行ったり、
ワーグナー音楽祭に出かけたりしていた。
だからこそ、
”アート”と言う言葉を使ったのではないかと思う。
芸術や美術に関して自分は無知だが、
藤澤氏の「経営はアートである」を自分なりに考えると、
「経営は人の心である。」と言っているような気がする。
人を感動させる美術品や芸術品には、
作者の熱意や心がこもっていると思う。
だからこそ、
人を引き付ける魅力が宿っているのだと思う。
経営は、人が行うモノであって、そこには組織が必要不可欠。
そして、組織は人が構成するもの。
人を引きつけ、魅了する組織は、どんな組織か?
その答えが、「人の心」ではないかと思う。
人の心を大切にすると言う事は、
藤澤氏の言葉を借りれば
「社員の働く意欲に正面から答える」
と言う事になるのではないかと思う。
従業員一人一人、個性があり、長所・短所がある。
それをどう活かすかは、
経営者の経営手腕であり、個々を活かす為の組織作りではないかと思う。
ホンダで言えば、
個々の個性を伸ばす為に研究所の分離独立をして、
独特な組織体制を作った。
どんなに技術が発達し、
いろいろな分野でコンピューターによる効率化が行われようとも、
人の心が通っていない組織には、
人を引き付ける魅力など生まれないと思う。
そして、人を引き付けないと言う事は、
会社に優秀な人材も入ってこず、
会社の成長も鈍り、停滞し、最終的には業績悪化を
招く事になるのではないかと思う。

会社組織である以上、従業員すべてに対応するのは不可能だと思う。
不可能だからと言って努力をしなくては、何も前に進まない。
むしろ、人の心は離れていくのではないかと思う。
努力と言う行動に示してこそ、
経営者の心が組織全体に伝わり、
従業員の心を引き付ける組織が生まれるのではないかと思う。


初めての方へ

現場力メソッド

経験知