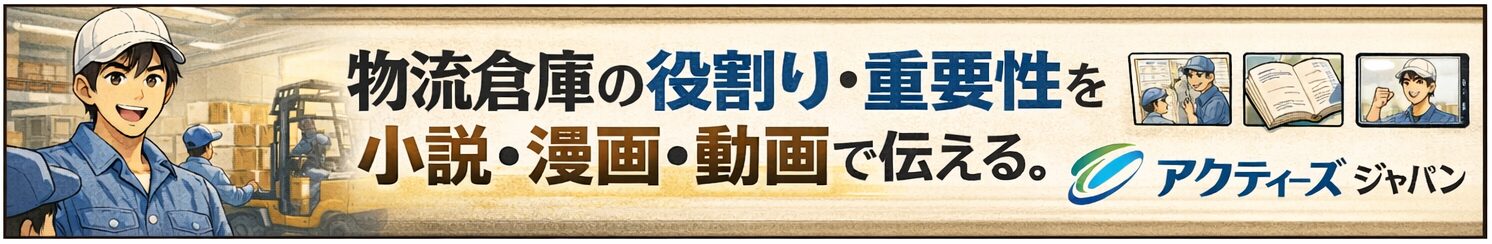お仕事小説「誰が現場を見ているのか」

第一章:見えない現場
「もう、限界かもしれんな……」
運送会社「新誠運輸」の社長・三崎誠司は、冷たい缶コーヒーを片手に帳簿を眺めていた。
ここ数年、価格競争が激化し、荷主はより安い運送会社に次々と乗り換えていった。
残った案件も、運賃はカツカツで、利益は薄い。
「うちは荷役作業やりません」
「ドライバーが責任を負う作業じゃありませんから」
現場での声も当然だ。法的にも、労働管理的にも無理は言えない。
けれど、誠司には一つ引っかかることがあった。
「俺たちは、荷物を運んでるけど、“現場”は誰が見てるんだ?」
⸻
第二章:製麺所の再起
ある日、昔の友人・藤岡から連絡が来た。
経営難だった彼の製麺所が、今は「特注麺」の製造で盛況だという。
「ラーメン屋が“こういう麺がほしい”って言ってきてさ。最初は無理だって思ったけど、現場で粉の違いを見て、水分量を変え、太さ、硬さを変えて、やっと納得いくもんができたんだ」
藤岡は笑いながら言った。
「依頼人の声と、現場の感覚があったから、ここまで来れたよ」
それを聞いた誠司の脳裏に、ふと、ある疑問がよぎった。
「俺たち……現場を、見てないかもしれない」
⸻
第三章:「触れないことで、見えなくなるもの」
誠司は若手ドライバー・望月と話をした。
「荷役、やりたくないのは分かる。でも、あそこで見えることって、実はすごく多いと思うんだ」
「例えば?」
「商品がどう並んでるか。破損の可能性。冷蔵庫の温度。荷主の困りごと。全部、納品の“その場”にしかない情報だよ」
望月は、しばらく黙っていたが、こう答えた。
「……それ、俺たちに求められてる“運ぶ”とは違うかもしれないですね。でも、“気づく”って意味では、確かにそうかも」
⸻
第四章:「運ぶ+気づく」という新しい価値
誠司は思い切って社内に提案した。
「荷役を“ただの作業”じゃなく、情報収集の場にしてくれないか?
やる・やらないの判断は自由だ。でも、やってくれた人には“別の評価軸”をつくる」
数人のベテランは反対したが、若手や現場を理解する中堅ドライバーが応じてくれた。
誠司はその人たちに、現場レポートを簡単に記録できるアプリを導入。
「現場で気づいたこと」「違和感」「困りごと」などを記録してもらうようにした。
すると、ある荷主から連絡が来た。
「新誠さん、先月レポートしてくれた“温度異常”のおかげで、大口クレームを回避できました。
……うちの担当より、よく現場を見てますね」
⸻
第五章:役割を超えるプロフェッショナル
「やっぱり、荷役は俺らの仕事じゃない、って今でも思う」
椎名は笑いながら言った。
「でもな、あの“ちょっとした違和感”に気づいて、荷主に感謝される。
その時に初めて、“プロ”になれた気がするんだよな」
—
新誠運輸は、今や“情報を運ぶ運送会社”として、荷主の信頼を集めている。
それは、価格ではなく、“現場を見てくれる安心感”で選ばれている証だった。
製麺所が「手で感じた麺の個性」で生まれ変わったように、
運送会社も「現場に触れる覚悟」で価値を創り直したのだ。
⸻

初めての方へ

現場力メソッド

経験知